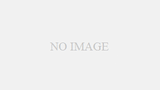単身世帯(一人暮らし)が増加し、今後も増えていくことが予想されているようです。
増えているのは、若者の一人暮らしではなく、未婚の中高年男性の一人暮らしや、
配偶者と死別した高齢者の一人暮らしが急増しているそうですが・・・
いったい何故・・単身世帯は増加してゆくのでしょうか?
単身世帯の増加と求められる対応
私も母子家庭、単身世帯で35年余活きて、要介護となった場合のリスク、貧困のリスク、社会的に孤立するリスクが高まっていくと考えられる現状に、社会としての対応が
求められている中で、どう対応してゆけばいいのか?
これまで結婚をして同居家族がいることを「標準」としてきた日本社会において、
単身世帯の増加は、社会に少なくない影響を与えていくとも言われ、
ライフスタイルの選択肢が多様になっていく一方で、間違いなく・・・
年々歳を重ねて・・団塊世代が後期高齢者になった時、街は年寄りばかり~~ww
単身世帯の現状と将来推計
2010年、全国の単身世帯数は1,678 万世帯、総人口の 13.1%を占めています。
2030年、になると、単身世帯数は 1,872 万世帯、総人口の 16.1%となると
みられています。
ここで・・注目すべきことは・・・
2010 年から 2030 年にかけて年齢階層別の単身世帯数の増減が大きい点です。
具体的には、2010年、男性で最も多くの単身世帯を抱えているのは20代!
何故20代の単世帯が多いのか?
20代で単身世帯が多いのは、多くの若者が進学や就職などを機に親元を離れて
一人暮らしを始めるためだそうです。
そして 30代以降、年齢階層があがるにつれて、単身世帯数は減少していきます。
結婚をして二人以上世帯となるためですが・・・
女性をみると、20代だけではなく、 70代で単身世帯が多くなっています。
70代で単身世帯が多いのは?
70代女性で一人暮らしが多いのは、女性の平均寿命が男性よりも長いので、
夫と死別して一人暮らしをする女性が多いことが要因でもあるようです。
2030年になると一変する理由は?
2030年になると、年齢階層別の単身世帯数は一変するのです。
20代の単身世帯は、少子化の影響を受けて男女共に大きく減少するとみられ、
2030 年に男性で最も多くの単身世帯を抱える年齢階層は 50代となるようです。
女性で単身世帯が最も多いのは 80歳以上となり、256万世帯にのぼると推計されて
いるのです。
驚いたことに・・・・ウヒョォォォォォ(°0°)!!。
2010 年の 80歳以上の単身女性数(125 万世帯)の 2倍の水準です。
2030年といえば団塊世代が後期高齢者となる時期です。
人数の多い「団塊の世代」が80 歳以上になることと、配偶者と死別した高齢女性が
子供と同居しない傾向が続くためと考えられるようです。
実際、夫と死別した80歳以上の女性のうち、子供と同居する人の割合は、
1995 年の 69.7%から、2010 年には 52.4%まで低下しているのです。
15年間で、配偶者を失った老親と子の同居率が、 17%も低下していると言うのも
時代の流れでしょうか?
何故?単身世帯は増加していくのか?
50代男性や、80歳以上女性で単身世帯がなぜ?増加していくのか?
50代男性で単身世帯が増加していく最大の要因は、未婚化の進展であると
言われています。
50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合を「生涯未婚率」と呼ぶそうですが、
男性の生涯未婚率
1985年まで 1~3%台で推移した後、
1990年以降、急激に上昇を始め、
2010 年には 20.1%となったようです。
つまり・・・50歳男性の5人に1人が未婚者のようです。
そして・・・ 2030年になると、男性の生涯未婚率は 27.6%になると
予測されているのです。
女性の生涯未婚率
女性の生涯未婚率は
2010年の 10.6%が
2030 年には18.8%になると推計されています。
女性の生涯未婚率も上昇していくようですが、男性ほど高い水準ではないようです。
老後の時間は刻々と延びている!?
単身世帯(20歳以上70歳未満)は、老後の生活について
●非常に心配である(50.9%)
●多少心配である(33.6%)
84.5%が心配と答えています。
年金では日常生活もまかなえないと考えている単身世帯が60%!
老後の生活費の収入源は?
1位=年金(54.8%)
2位=就業による収入(44.2%)
3位=企業年金、個人年金、保険金(27.5%)
4位=金融資産の取り崩し(24.0%)」
その他=国や市町村などからの公的援助(10.0%)
歳とともに・・自助努力は限界と考える世帯もある中で、公的援助と子ども世帯に
余裕がなくなりつつある現状で単身世帯に限らず、老後の生活は元気なうちに
将来を見据えてしっかりと考えておかなければいけないようです。
まとめ
極貧母子家庭を経て、単身世帯で長年暮らしてきて・・・
その日暮らしで日々賄ってきたような、あまり将来のマネープランを
考える生活の余裕のないまま今日に至っているような・・・
ただ・・・貯蓄枠のない生活の中で「厚生年金」「健康保険」「失業保険」
福利厚生が整備されている「正規雇用」を選んで働いてきました。
しかし・・・「年金額」だけでは暮らしてはいけません!
終身現役を貫く精神で【健康】が一番ですね~~
一魂こめて・・